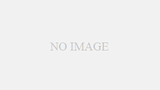副業ライターとして、初めて案件を受注したとき。
正直めちゃくちゃ嬉しかったです。
「ついに自分でも仕事が取れた!」って。
でも…実際に作業が始まってみると、
「思ってたより、全然時間が足りない…」という焦りがどんどん湧いてきました。
納期まで1週間あるし、余裕でいけるだろうと思ってたんです。
でも、執筆→提出→修正…とやっているうちに、あっという間に期限目前。
しかも、クライアントとのやり取りにも時間がかかる。
「副業ライターって、案件を取るだけじゃないんだな」
そんな気づきが、受注後のリアルな第一歩でした。
この記事では、僕が実際に体験した3つの案件を通して、
「受注後にどう動くのか」「何が大変だったか」「どんな工夫をしたか」をまとめています。
これから副業ライターとして前に進みたい方の、ヒントになればうれしいです
案件を受注して気づいた“想像とのギャップ”
副業ライターとして初めて案件を受けたとき、
正直、「これなら1週間あれば余裕で終わるでしょ」と思っていました。
でも、現実はまったく違いました。
余裕だと思った納期が意外とギリギリ
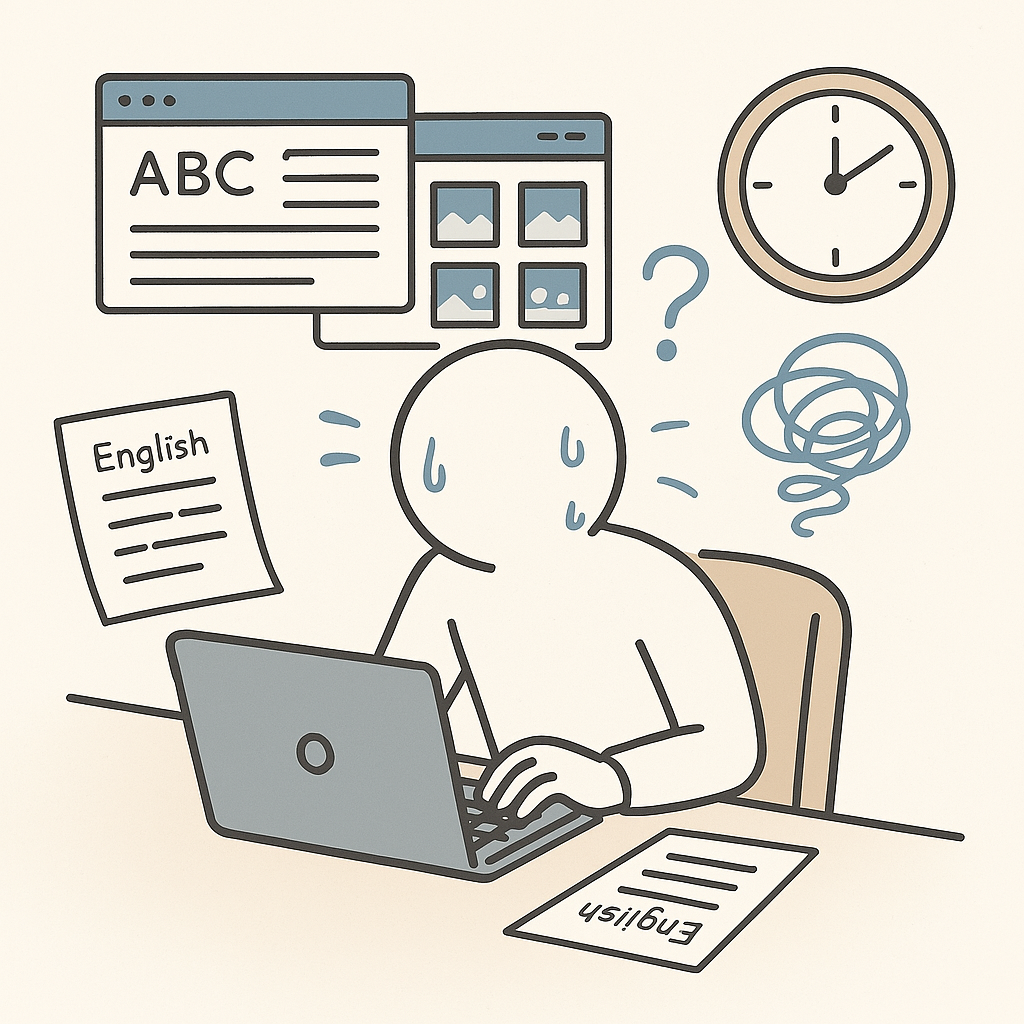
1週間の納期って、結構長いように見えますよね。
でも、いざ取りかかってみると、構成を考えるだけで1日、執筆に2日、提出してから修正依頼が来て…
「気づいたらもう締切前日!」みたいなことが何度かありました。
しかも、こちらが提出してもすぐに返事が来るとは限らない。
中には、修正指示が届くまでに2〜3日かかった案件もあって、想定していたスケジュールが一気に崩れたことも。
「意外と時間がない」
このギャップに最初はかなり焦りました。
やり取りのペースも“自分次第”じゃないと実感
会社員の仕事だと、上司や同僚と毎日顔を合わせているし、相談もしやすいですよね。
でも副業ライターの仕事って、基本は非同期のやり取り。
メッセージを送っても、すぐ返事が来るとは限らない。
こちらとしては「早めに修正して納品したい」と思っていても、
相手の返信が遅いと、こちらの動きも止まってしまう。
そのことに気づいてからは、余裕を持って動くことや、先回りして確認することを意識するようになりました。
案件をこなすことで初めて「ライターの仕事」が見えてきた
実際にやってみて感じたのは、
案件を受けてからが“本当のスタート”だったんだなということ。
・どこまでリサーチするか
・構成をどう組むか
・どう伝えるとクライアントに安心してもらえるか
最初は何もわからなかったけど、やってみて初めてわかることばかりでした。
「受注できたらゴール」じゃなくて、
「受注してからが、ライターとしての本番」なんですよね。
実際に体験した3つの案件レポート
案件①:学校情報まとめ(リサーチ+地味に時間がかかる)
最初に受注したのは、指定された学校の情報をまとめるリサーチ系のライティング案件でした。
いわゆるトライアル案件で、最初は5件まとめて2,500円(1本あたり500円)。正直、単価としてはかなり低めです。
作業の流れとしては、指定された学校について、公式サイトなどをもとに指定フォーマットに沿って入力していくというものでした。
文章をゼロから書く必要はなく、項目に沿って埋めていく形式なので、やる前は「これはサクッとできそう」と思ってました。
…ところが、実際にやってみると、意外と時間がかかる。
例えば、どこに校舎があるのか、コースの内容、特色ある取り組みなど、正確な情報を探すのに意外と手間がかかりました。
サイトのどこに何が書いてあるかもバラバラで、学校によって情報の出し方が全然違うんですよね。
一通り作業を終えたあと、ふと気になって計算してみたんですが、
「これ…時給換算したら500円くらいかも」とちょっと複雑な気持ちになりました。
でも、未経験の自分が初めて受けた案件としては、「納品までやりきれた」ことが何より大きかった。
「一文字一文字に責任を持つ」ってこういうことか、と実感できた経験でもありました。
案件②:ブログ記事執筆(英語元記事・画像探しで苦戦)
2つ目に受けたのは、英語の元記事をもとにブログ記事を執筆する案件でした。
内容は「指定された英語メディアの記事を参考にしながら、日本語でわかりやすくまとめてほしい」というもの。
納品形式はWordPressへの直接投稿で、画像挿入や見出し設定まで含まれていました。
文字数は約2,000〜2,500文字。
「テーマ自体はわかりやすいし、構成もある程度決まっているから、書くだけならいけるかな」と思っていたのですが…
実際は想像以上に手間がかかりました。
まず、元記事がすべて英語だったので、翻訳が必要。
AI翻訳を使えばざっくり意味はつかめるんですが、
細かいニュアンスや正確さを確認するために、自分でも英文をチェックし直す必要がありました。
さらに大変だったのが、画像の挿入。
「できればフリー素材ではなく、元記事に近い雰囲気の画像を使ってほしい」という要望があったため、
海外のフリー画像サイトや元記事の引用元を探して、“日本語ではヒットしない”検索を英語でやる必要がありました。
この作業が地味に時間がかかって、
「1記事にここまで手間をかけるとは思わなかった…」というのが正直な感想です。
ただ、この案件は継続案件として依頼をいただけることになり、
現在も月2本ペースで継続中です。(1本あたり2,500円程度)
「作業は大変だけど、納品後に信頼してもらえた」
この経験が、自分の中でも「やってよかった」と思える大きな出来事になりました。
LPライティング(ヒアリング〜納品まで)
3つ目に受けたのは、商品のランディングページ(LP)を作成するライティング案件でした。
これは1回限りのスポット案件で、構成から執筆、修正対応までをすべて任される形。
正直、緊張感もありました。
というのも、セールス要素のある文章はこれが初めて。
LPは「魅力を伝えつつ、行動につなげる」構成が求められるので、普段の記事よりも“売る視点”が必要です。
まず最初にやったのは、商品の理解に努めること。
クライアントから資料がいくつか共有されていて、それを丁寧に読み込みました。
「この商品は誰にとって、どんな価値があるのか?」
「実際に使った人はどんな感想を持つのか?」
など、内容をよく理解してから構成に取りかかることで、
文章に“説得力”が出てくる実感がありました。
その後、他社LPの流れも参考にしつつ、
読者の感情の動きに合わせた構成を考えて執筆。
「もっとこうした方が伝わるかも…」と悩みながらでしたが、納期より1日早く提出しました。
クライアントからの反応はというと…
実は、特にフィードバックはありませんでした。
こちらからの提出後、「ありがとうございました」という返信があっただけで、
良かったのか、イマイチだったのか、手応えは正直なかったというのが本音です。
継続の話も出なかったので、もしかしたら満足してもらえなかったのかもしれません。
それとも、一度きりの依頼だったのか。
ただ、この経験を通して思ったのは、
「フィードバックって、本当に大事」だということ。
褒め言葉が欲しいわけじゃなくて、
「何がよかったのか」「どこを直せばもっと良くなるのか」
それがわかれば、次に活かせるからです。
未経験ライターとして感じたこと・学んだこと
実際に3つの案件を経験してみて、改めて思ったのは——
「案件を取ってからのほうが、本当の意味で学びが多い」ということです。
受注後の動きこそ“ライターとしての力”が問われる
案件に応募して、運よく受注できたとしても、そこからが本番。
構成を考えて、リサーチして、執筆して、納品して、修正対応もして…
クライアントとのやりとりも含めて、「一人のライターとして信頼されるかどうか」が試されている感じがしました。
予定より時間がかかる前提でスケジュールを組む
どの案件も、やってみると想像以上に時間がかかりました。
執筆だけでなく、やりとりの待機時間や修正対応も含めると、
「納期ギリギリでやろう」なんて考えていたら、すぐに詰まります。
今はもう、最初の頃より余裕を持って作業をスタートするようにしています。
“納期に間に合わせる”じゃなくて、“安心してもらえる動き方”を意識するようになりました。
クライアントとの信頼構築は“やり取りの丁寧さ”から始まる
案件をこなしていく中で一番実感したのは、
「この人、ちゃんとしてるな」と思ってもらえるやり取りが、信頼につながるということ。
たとえば…
• 「納期○日ですが、○日までにドラフト提出予定です」と先に伝えておく
• 迷ったときは「こちらの解釈で合っていますか?」と確認を入れる
• 返信が遅れそうなときは「○時ごろお返事いたします」と一言添える
• 修正依頼が来たら「ご指摘ありがとうございます」と感謝から入る
こうしたやり取りって、地味だけど本当に大事だなと感じました。
こちらとしては「文章で勝負している」つもりでも、
クライアントからすれば、安心して任せられるかどうかは“やり取りの印象”で決まる部分も大きいと思います。
クライアントから「信頼されてるな」と明確に感じた場面は、正直まだ少ないです。
でも、納品後に大きな修正がなかったり、継続依頼をもらえたりすると、
「あ、ちゃんと伝わったんだ」「もう一度お願いしたいと思ってもらえたのかも」と思えて、少しずつ自信になってきました。
学校紹介の案件も、結果的には継続は選びませんでしたが、
クライアントから「次回もお願いします」という案内があったことで、ちゃんと評価はしてもらえていたのかなと思います。
こうした小さなやりとりの積み重ねが、自分にとっても「次はもっと良くしよう」と思える原動力になっています。
今後に活かしたい改善点と目標
案件をいくつか経験してみて、
「なんとなくできた」では終わらせたくないという気持ちが強くなってきました。
だからこそ、これまでの経験を次にどう活かすかをしっかり考えていきたいと思っています。
案件ごとに時間配分を見直すクセをつける
最初の頃は、「このくらいの作業量なら大丈夫だろう」と軽く見積もってしまっていました。
でも実際には、クライアントとのやり取りや修正対応、リサーチの深さなどで、予想以上に時間がかかることが多い。
これからは、「納期まで余裕がある=安心」ではなく、
工程ごとにかかる時間を見積もって、スケジュールを組むクセをつけたいと思います。
自分の強みや相性が良いジャンルを意識する
案件をこなす中で、「やりやすい」と感じるジャンルと、やたら時間がかかるジャンルがあることにも気づいてきました。
自分の場合、セールス系のLPよりも、リサーチ+記事化のほうが自然に書ける感覚があります。
だからこそ今後は、無理に何でも挑戦するよりも、自分に合った案件を見極めていく視点も大事にしたいです。
「自分の得意」が見えてくると、仕事の進みも変わってくる気がしています。
もっと効率よく、でも誠実にこなせるライターへ

今はまだ、作業に時間がかかってしまうことが多いです。
でも、それを**「不器用だけど丁寧だった時期」として経験値にしていくことが大事**だと思っています。
少しずつ経験を重ねながら、
無駄を減らしつつ、誠実さはそのままに——
クライアントから安心して任せてもらえるライターになれるよう、これからも改善と挑戦を続けていきたいです。
まとめ|未経験でも、やってみれば見えてくる
副業ライターとして、初めて案件を受注したときは嬉しかった反面、
「あれ?想像と違うぞ…」というギャップの連続でした。
特に印象的だったのは、
• 納期は余裕があると思ったら、全然足りない
• リサーチや翻訳は、見た目以上に手間がかかる
• “文章力”だけでなく、やり取りや姿勢も評価される
という点。
でも、そういった経験を通して、
「受注できたらゴールではない。そこからが本番」いうことを強く実感しました。
これからライターを目指す人にとって、
この記事が少しでもリアルな働き方のイメージにつながったならうれしいです。
次回予告|受注率を上げたい。僕が提案文を見直した理由
さて、次回の記事では…
**「なかなか案件が取れない」**という悩みに向き合って、
実際に僕がやってみた提案文の改善や、ポートフォリオの見直しについて紹介する予定です。
など、「どうしたら受注につながるのか?」という課題に対して、試行錯誤してきたリアルな過程をお届けします。
未経験でもできる、改善のヒントを知りたい方は、ぜひお楽しみに!